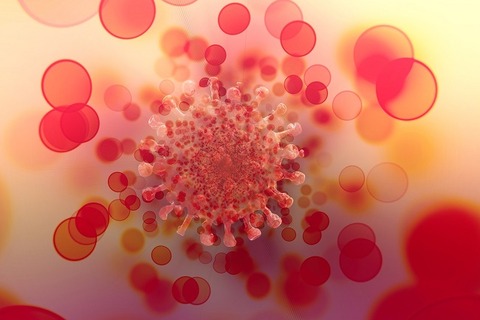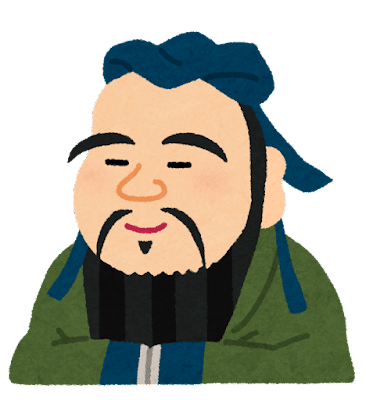国が違えば、人種が違い言葉が違い文化も習慣も何もかも違う。当たり前の話である。ある人は、人間は全ての違いがあるにもかかわらず、結局は誰も皆同じであると言う。またある人は逆に、人間は人種や言葉や文化や習慣などが違うために、お互いに本当に理解し合うことはできないと主張する。それはどちらも正しく且つどちらも間違っている。なぜなら人種や言葉や文化や習慣の違う外国の人々は、決してわれわれと同じではあり得ず、しかもお互いに分かり合うことが可能だからである。
世界中のそれぞれの国の人々は他の国の人々とは皆違う。その「違う」という事実を、素直にありのままに認め合うところから真の理解が始まる。これは当たり前のように見えて実は簡単なことではない。なぜなら人は自分とは違う国や人間を見るとき、知らず知らずのうちに自らと比較して、自分より優れているとか、逆に劣っているなどと判断を下しがちだからである。
他者が自分よりも優れていると考えると人は卑屈になり、逆に劣っていると見ると相手に対してとたんに傲慢になる。たとえばわれわれ日本人は今でもなお、欧米人に対するときには前者の罠に陥り、近隣のアジア人などに対するときには、後者の罠に陥ってしまう傾向があることは、誰にも否定できないのではないか。
人種や国籍や文化が違うというときの”違い”を、決して優劣で捉えてはならない。”違い”は優劣ではない。”違い”は違う者同士が対等であることの証しであり、楽しいものであり、面白いものであり、美しいものである。
僕は今、日本とは非常に違う国イタリアに住んでいる。イタリアを「マンジャーレ、カンターレ、アモーレ」の国と語呂合わせに呼ぶ人々がいる。三つのイタリア語は周知のように「食べ、歌い、愛する」という意味だが、僕なりにもう少し意訳をすると「イタリア人はスパゲティーやピザをたらふく食って、日がな一日カンツォーネにうつつを抜かし、女のケツばかりを追いかけているノーテンキな国民」ということになる。それらは、イタリアブームが起こって、この国がかなり日本に知れ渡るようになった現在でも、なおかつ日本人の頭の中のどこかに固定化しているイメージではないだろうか。
ステレオタイプそのものに見えるそれらのイタリア人像には、たくさんの真実とそれと同じくらいに多くの虚偽が含まれているが、実はそこには「イタリア人はこうであって欲しい」というわれわれ日本人の願望も強く込められているように思う。つまり人生を楽しく歌い、食べ、愛して終えるというおおらかな生き方は、イタリア人のイメージに名を借りたわれわれ自身の願望にほかならないのである。
そして、当のイタリア人は、実は誰よりもそういう生き方を願っている人々である。願うばかりではなく、彼らはそれを実践しようとする。実践しようと日々努力をする彼らの態度が、われわれには新鮮に映るのである。
僕はそんな面白い国イタリアに住んでイタリア人を妻にし、肉体的にもまた心のあり方でも、明らかに日伊双方の質を持つ二人の息子を家族にしている。それはとても不思議な体験だが、同時に家族同士のつき合いという意味では、世界中のどこの家族とも寸分違わない普通の体験でもある。
日本に帰ると「奥さんが外国人だといろいろ大変でしょうね」と僕は良く人に聞かれる。そこで言う大変とは「夫婦の国籍が違い、言葉も、文化も、習慣も、思考法も、何もかも違い過ぎて分かり合うのが大変でしょうね」という意味だと考えられる。しかし、それは少しも大変ではないのである。僕らはそれらの違いをお互いに認め合い、受け入れて夫婦になった。違いを素直に認め合えばそれは大変などではなく、むしろ面白い、楽しいものにさえなる。
日本人の僕とイタリア人の妻の間にある真の大変さは、僕ら夫婦が持っているそれぞれの人間性の違いの中にある。ということはつまり、僕らの大変さは、日本人同士の夫婦が、同じ屋根の下で生活を共にしていく大変さと何も変わらないのである。なぜなら、日本人同士でもお互いに人間性が違うのが当たり前であり、その違う二人が生活を共にするところに「大変」が生じる。
僕らはお互いの国籍や言葉や文化や習慣や何もかもが違うことを素直に認め合う延長で、人間性の違う者同志がうまくやって行くには、無理に“違い”を矯正するよりも「違うのが当然」と割り切って、お互いを認め合うことが肝心だと考え、あえてそう行動しようとする。
それは一筋縄ではいかない、あちこちに落とし穴のある油断のならない作業である。が、僕らは挫折や失敗を繰り返しつつ“違い”を認める努力を続け、同時に日本人の僕とイタリア人の妻との間の、違いも共通点も全て受け継いで、親の欲目で見る限り中々良い子に育ってくれた息子二人を慈しみながら、日常的に寄せる喜怒哀楽の波にもまれて平凡に生きている。
そして、その平凡な日常の中で僕は良く独(ひと)りごちるのである。
――日本とイタリアは、この地球上にたくさんある国のなかでも、たとえて言えば一方が南極で一方が北極というくらいに違う国だが、北極と南極は文字通り両極端にある遠い大違いの場所ながら、両方とも寒いという、これまた大きな共通点もあるんだよなぁ・・・――
と。